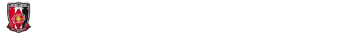
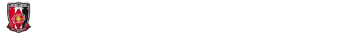

2007年1月、クラブが新しい年、新しいシーズンをスタートするにあたって、当時の浦和レッズ代表・藤口光紀は「Jリーグ連覇とACL制覇」を口にした。
「絶対に優勝しなければいけない」
その言葉の強さに、クラブスタッフは一瞬驚き、次の瞬間には身の引き締まる思いがした。
前年、レッズはギド・ブッフバルト監督の下、最終戦でガンバ大阪を下して念願のJリーグ初優勝を成し遂げていた。
この年はホルガー・オジェック新監督を迎え、Jリーグ連覇だけでなく、初めて出場するAFCチャンピオンズリーグ(ACL)でも優勝を飾り、
年末に日本で行われるFIFAクラブワールドカップへの出場権を獲得しようと、目標を打ち上げたのだ。
「人間は常に新しいものに挑戦していかないと停滞してしまう。日本で優勝したら次はアジアだ、世界だというのは、サッカーで生きている人間である限り当然だと思いました」(藤口)
「ところが当時、日本のクラブは、『ACLは負担ばかり大きくて困る』という見方が大半だったんです」
2002/2003シーズンに第1回大会が行われ、2004年から単年の大会となったACL。
欧州で大成功しているUEFAチャンピオンズリーグのような成功を夢見て始められたものだったが、海外遠征の金銭的・肉体的負担が大きい割に日本国内では認知度が低く、入場者数もまったく伸びなかった。
あるクラブは、ACLだけは通常のJリーグで使っているのと違う収容数の少ないスタジアムを使用し、ともかく経費を削減しようとした。
当然、チームも力がはいらず、2007年にレッズが初出場するまで、4シーズンでJリーグから延べ8クラブが出場していたが、グループステージを突破したチームはひとつもなかった。
こうした状況に強く反発したのが藤口だった。
「アウェーで引き分け、ホームで勝てば、必ず優勝できる」
ホームで勝つためのカギは、サポーターにあると考えた。前年、Jリーグ初優勝が現実的になり始めたとき、
藤口はチームを後押しするためにホームの埼玉スタジアムを満員にしようと、「ALL COME TOGETHER」というキャンペーンを始めた。
プレッシャーがかかった最終節の埼スタで選手に力を与えたのは、当時のJリーグ記録の6万2241人のサポーターの圧倒的な声援だった。
「浦和レッズというのはひとつの『サッカークラブ』ですが、強化部を中心にオジェック監督が指揮をとる『チーム』は、専門家の手に任されています。
では『クラブ』としては何ができるか。満員のスタジアムが最大の後押しになるというのが、私の考えでした。他のクラブは『ACLは観客がはいらない』と言っていましたが、
私は何が何でも埼スタを満員にしようと思いました」
3月7日、インドネシアのペルシク・ケディリを迎えた初戦は、気温が10度を切る寒さだったが、3万1303人のサポーターが熱い声援を送った。
グループステージ最終戦のシドニーFC(オーストラリア)戦には4万4793人が集まり、準決勝の城南一和(韓国)戦は5万1651人、
そして決勝のセパハン(イラン)戦は5万9034人。藤口の願いどおり、満員のサポーターがつくり出した圧倒的な雰囲気が選手たちに体の底から湧き上がるような力を与えた。
アウェーは6戦して1勝5分け。ホームは4勝2分け(1PK勝ち)。城南との準決勝では、アウェー、ホームとも2-2の引き分けとなり、
PK戦で決勝進出チームが決められることになった。延長前半に交代したDF山田暢久に代わってキャプテンのアームバンドを巻いていたDF坪井慶介は、
コイントスに勝つと迷うことなくレッズ・サポーター側のゴールを選んだ。
果てしなく繰り返される「ウィー・アー・レッズ!」の声援が疲れ切った選手たちの足に最後のパワーを与え、GK都築龍太に冷静な判断力を与えた。
先攻のレッズは5人全員が決め、城南の2番手・崔成國が中央上に強くけったボールを都築は一歩も動かずにはじき出した。
サポーターの力をチームの力にする—。藤口の思いどおりの優勝だった。だがサポーターの力は、ホームにとどまらなかった。
文・大住良之
(下に続く)
藤口光紀(ふじぐち・みつのり)
広島経済大学経済学部スポーツ経営学科教授、広島県サッカー協会副会長。2006年6月〜2009年4月、浦和レッズ代表。
1949年群馬県勢多郡粕川村(現前橋市)生まれ、68歳。慶応義塾大学を経て1974年に三菱重工に入社、日本サッカーリーグで127試合に出場し、27得点。
切れ味鋭いドリブル突破でチャンスメーカーとして活躍した。日本代表Aマッチ26試合出場、2得点。
1982年に現役引退後、慶応大学ソッカー部監督を務め、1993年から浦和レッズで事業広報部長などを歴任した。